【青森・函館旅行日記 2日目】八戸市編
皆様、明けましておめでとうございます!
今回は、新婚旅行記2日目、八戸の旅について書きたいと思います。昨年から転勤やらなんやかんやとバタバタしてしまっており、すっかり遅くなっています。。苦笑 相変わらずのマイペース更新ですが、今年も是非とも、お付き合いいただけますと幸いです。
1.青い森鉄道
2日目は、朝早起きして、八戸に出発です!青森から八戸まで、青い森鉄道に乗って1時間半ほどかけて向かいます!
この青い森鉄道は、かつて東京〜青森を結んでいた、JR東日本東北本線の一部でしたが、東北新幹線が開業した2002年に青森駅〜目時駅(青森県三戸市)の区間が第3セクターとして分離独立したローカル線です。

▲青い森鉄道の正面からの写真。真ん中に見えているキャラクターは「モーリー」
当時乗客数の少なくなっていた当区間が、東北新幹線の開通に伴い分離されたとか(諸説あり)。おまけにその新幹線と重複するため、主力であった寝台特急の運行ができなくなるという状況でした。このような、元々の経営難に加え収益源を廃止せざるを得ないという逆境から、青い森鉄道はスタートしました。
このような状況だったこともあり、JRから分離する際に自治体からも援助策も立案され、線路部分(下部)が青森県、鉄道事業(上部)を青い森鉄道が分担して運営を行う、「上下分離方式」を日本の第三セクター鉄道として初めて採用した路線となりました。

▲青い森鉄道の横からの写真。ピンクのモーリーもいる?!
ところがそんな逆境にあっても、青い森鉄道は軌跡の復活を遂げます。特産品を地元の農家や商店が車内で販売する「あおてつマルシェ」、地酒を楽しめる貸し切り屋台列車「酒のあでゆきみ列車」など、観光客の取り込み施策・工夫、また駅や本数の合理化と青森県との連携による学校の移転事業などを経て、近年では乗客数が回復してきているとの事です。この青い森鉄道の成功事例は、ローカル線の苦境が取り沙汰される今日において、鉄道経営の成功例として今も熱い注目を浴びているそうです!鉄道好きの筆者としては、今後も頑張ってほしいです!!
2.八戸の歴史
さて、電車が八戸に着くまでの間に、八戸の歴史についてまとめたいと思います。
①八戸(はちのへ)の名前の由来
そもそも八戸という名前の由来は何でしょうか?実は、“〜戸“がつく地名は、東北地方の特に青森〜岩手に数多く存在します。調べてみたところ一戸〜九戸までが存在し(四戸は存在しない。理由は諸説あり面白そうだったのですが脱線するので割愛。)、この“〜戸“という呼び方は平安時代後期に、前九年の役・後三年の役〜奥州藤原氏の時代の東北地方での行政区として確立したそうです。つまり、八戸がその頃から存在していたとすると約1100年近くの歴史ある町と考えられます!
②南部氏の治世
その後、源頼朝が奥州藤原氏を滅ぼした奥州合戦で功を立てた南部光行(なんぶみつゆき)にこの地が与えられました。南部光行は甲斐(現在の山梨県)の南部という土地に定着していた武田家の一族、つまり甲斐源氏に区分される名門家系です。南部氏はその後、東北屈指の大名として南北朝・戦国・江戸・明治時代を生き抜き現在まで存続している数少ない名門家です。筆者はかつて、「なんで日本の一番北にいるのに南部やねん。」とよく思っていたものですが(笑)、この名前は南部氏の発祥の地(現山梨県南部町)に由来するそうです。

▲南部氏の最盛期。そのあまりにも広大な支配地域から、「三日月の 丸くなるまで 南部領 (南部領を通る間に月が三日月から満月になるという意味)」と称えられた。
八戸はそんな南部氏率いる盛岡藩・八戸藩の交通の要衝として、江戸時代に繁栄を迎えます。八戸港は東廻り航路の重要拠点となり、江戸時代に起きた物流網の飛躍的発展の恩恵を受けました。また漁港としてもイカ・サバ・イワシを中心に水揚げ高全国トップ10の常連で、昭和からの統計で全国1位になった事も6度ある国内屈指の港町です。

▲八戸港の航空写真(八戸港湾・空港整備事務所HPよりhttp://www.pa.thr.mlit.go.jp/hachinohe/hachinohekou/02gaiyou.html)
③明治後の八戸市
また、水産加工業のみならず、戦前から製鉄業など良港を必要とする産業が発展し、戦後に国から新産業都市に指定されると八戸港と豊富な水源を活かした製紙産業が新たに成長しました。このように八戸市は青森県の歴史・産業の両方において非常に重要な市なのです。今回の旅を通して、今まで知らなかった産業立国、青森の一面を新たに知ることができました。
3.八戸に到着!
①陸奥湊
さて、青森から八戸に着いたのは朝8時ごろ、八戸のオススメは朝ご飯に食べる海鮮とガイドブックに書いてあったので、陸奥湊(むつみなと)へ!

陸奥湊では、毎週日曜日朝に全国最大規模の朝市、館鼻岩壁(たてはながんぺき)朝市が開催されるのですが、今回は旅の日程の都合上訪れることはできませんでした。。泣

▲館鼻岩壁朝市は、全長約800m、およそ300店が立ち並び7万人の人々が訪れる全国最大規模の朝市。https://www.ana.co.jp/ja/jp/japan-travel-planner/aomori/0000025.html
そこで、今回は陸奥湊の名店として有名な 「みなと食堂」さんで美味しい海鮮丼をいただきました!駅前の魚屋さんが立ち並ぶ通りにある、レトロな建物の中にあるそのお店は、朝8時半の時点ですでに行列ができていました!

▲みなと食堂の店構え。道を挟んで反対側で順番待ち。
1時間ほど待って入店すると、沢山のメニューがあり迷った末に、漁師の漬け丼(かに・ホタテ・いくら・たこ・マグロ・甘エビ・つぶ貝・サーモン・カジキマグロ・イカで¥1,850)を注文しました!!新鮮な甘味のある魚たちは、自慢の漬けダレでしっかり味付けしてあり、仕上げとばかりに卵のマイルドさが加わった至極の逸品でした!!

▲八戸が漁師の街であることを問答無用で納得させられる、ゴージャスな海鮮丼!
②種差海岸
新鮮な魚がたっぷりの海鮮丼で腹ごしらえを済まし、種差海岸(たねさしかいがん)へ!
種差海岸は、三陸復興国立公園に含まれ、リアス式海岸による海岸線や、650種を超える植物や樹齢100年の木々が自生している自然、春〜夏にかけて飛来するウミネコなど、その豊かな自然・風景から国の名勝にも指定されています。
陸奥湊駅からJR八戸線で30分ほど南へ進むと、大久喜駅という駅があり、そこから徒歩15分くらいで高岩展望台という穴場スポットがあります。車道の脇を歩いていくために、少々アクセスしづらいところに入口があります。それ故に、穴場と呼ばれるわけですね。。笑

▲高岩展望台の入り口。色んな意味でここで合っているのか不安になりました。笑
入口から林の中に続く階段と道を歩いていくと高岩展望台に到着・・・と同時に、三陸のリアス式海岸と太平洋の見事なコントラストが生み出す景色が目に飛び込んできました・・・・!!!夏の強い日差し、北国の涼しい風、眼下に広がる壮大な景色は、日ごろの喧騒を離れてリフレッシュさせてくれる、本当に爽やかな記憶を焼き付けてくれました。

▲絶景かな、三陸海岸!
高岩展望台を後にしたのち、海岸線の道を歩いて30分くらいで、種差海岸駅付近へ。そこには天然芝が養生してあり、自由に入ることができます。芝生に寝転がって、ウミネコの鳴き声と海の音を聞きながら暫くのんびりして、青森市への帰路に着くことにしました。

▲穏やかな気候と景色で、歩き疲れていたのもあって、ついウトウトしてしまいました。笑

▲レトロでこじんまりした種差海岸駅。
③八幡馬
八戸編の最後に、市内で購入した伝統工芸品である八幡馬を紹介します。

▲ちょっとエキゾチックでいてどこか懐かしい、可愛らしい置物、八幡馬!(株式会社八幡馬様HPhttps://www.yawatauma.co.jp)
発祥については諸説あるものの、古来より馬の産地として有名であった同地において、愛馬の順調な生育を願って木彫り馬を作る風習があったとのことです。
馬に塗られた模様は、昔の花嫁の嫁入り時に用意されていた盛装馬をイメージしていると言われ、結婚や新築、出産などお祝い事に広く用いられています。
素朴だが文化の香りがする、北奥羽の雄、南部家の本拠地に相応しい伝統工芸品で、大きさもコンパクトなのでお土産や記念にとても素敵な品だと感じました!
八戸の旅路は以上です!八戸市は全国有数の港がある街だけあって、工業と漁業の街という印象がありましたが、加えて豊かな自然も維持されている、青森県だけでなく日本にとっても非常に重要かつ貴重な資源に恵まれた土地であると感じました。
次回は、3日目に行った弘前市について書きたいと思います!
【青森・函館旅行日記 1日目】青森市編②
1.ねぶたの家 ワ・ラッセ
お昼過ぎに青森空港につき、シャトルバスで40分ほどかけて青森市へ。雪国らしいアーケードがついた商店街がメインストリートとなっています。駅近のビジネスホテルにチェックインを済ませて、青森名物ねぶた祭りに関連する博物館「ねぶたの家ワ・ラッセ」に向かいます。

▲青森空港から青森市街地へは、JRバス東北のシャトルバスがオススメ。30分〜1時間に1本、710円で運行しています。
「ねぶたの家ワ・ラッセ」は、ねぶた祭りの魅力を1年間通じて伝えられるように、というコンセプトで2011年に造られた施設です。“ワ“はねぶた祭りによって育まれる人の輪や和、“ラッセ“はねぶた祭りの特徴的な掛け声である、「ラッセラー!」という掛け声から名付けられています。

▲右側の赤い建物が、「ねぶたの家ワ・ラッセ」大人は620円・高校生は460円・小学生以下は260円。夏場は18時台でも入場できるのが旅行客には有り難い。
入場料を払うと、まず2階のねぶた祭りの歴史紹介から始まります。ねぶた祭りの起源は明確に解明されているわけではなく、いくつかの説が存在します。
・平安時代に、征夷大将軍坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)が蝦夷を提灯や太鼓や笛で誘き寄せて討伐したことが起源とする説。
・奈良時代に、中国から入ってきた七夕の節句が、日本の棚機津女(たなばたつめ)の神話と合わさり江戸時代に広く庶民に広がっていく過程で、青森ではねぶた祭りとして定着したものとする説。
・江戸時代初期に、弘前藩の初代藩主津軽為信(つがるためのぶ)が、お盆の時期に京都滞在した際、大きな提灯を飾らせたことが評判となったことを起源とする説。
などの説があります。

▲金魚ねぶたに誘われてタイムスリップしているかのように、ねぶた祭りの歴史コーナーの奥へと進んでいく。
2階の歴史コーナーを進むと突然大きな吹き抜けになっている「ねぶたホール」に行きつきます。そこには実際に過去のねぶた祭りに出陣し表彰をされたねぶたが展示されており、そのあまりの迫力に圧倒されてしまいました!!

▲「ねぶたホール」の写真。本番が見ることができない時に、ねぶた祭りの世界観に浸るにはこれ以上の場所はありません!日本の神話や御伽噺をテーマに豪華絢爛なねぶたに囲まれた空間は圧巻。
ねぶたの制作には、以下の段取りで1年を通して行われ、延べ300人近くのねぶた師や職人達の技術と想いが注ぎ込まれています。製作費は2000万円ほどと言われ、その8割近くが材料費や作業費に費やされます。また、祭りが地域に与える経済波及効果は280億円とも言われています。
9〜1月 題材(歌舞伎や神話、歴史など)の決定と下絵制作
2〜4月 細部の制作
4〜5月 ねぶたの制作と保管を行う小屋の建設
5〜6月 骨組み
7〜8月 電気配線・紙はり・墨書き・ろう書き・色付け
8月 台上げ
8月2日〜7日 本番

▲ねぶたの内側の展示。針金に和紙を貼って作られる。
コロナ禍の関係で残念ながら2020年・2021年のお祭りは中止となりましたが、2020年にねぶたの職人さんたちの生活とねぶた祭りの伝統を守るために、クラウドファンディングによる、ねぶた制作が企画されました。
その資金をもとに、14名の職人さん達によって制作されたねぶたが、下記写真の左側に陳列されている“特別ねぶた“です。疫病退散・病気平癒・魔除け・不屈の精神を表した、薬師如来・玄奘三蔵・十二神将が力強く躍動する、職人・題材ともに言わばオールスター制作となっています。

▲病と災禍を退け衣食住を満たす十二誓願を立てた薬師如来、中国からインドへ仏教を学びに行き苦難を乗り越え中国に仏教を布教した玄奘法師と、彼らを守護する十二神将が描かれている。コロナ禍の早期収束への願いと、逆境にも挫けずねぶたの火を絶やさぬ決意が込められている。
※あとがき
2022年にねぶた祭りは地元の人々の努力により、規模を縮小し平日開催としながらも、3年ぶりに開催されました。コロナ以前に比べると観光客は4割程度に落ち込んだそうですが、開催できたこと自体が、ねぶた祭りだけでなく青森に活気が戻るきっかけになって欲しいと、願うばかりです。
②青森での最初のディナー!
さて、青森の名産としては養殖ホタテが代表格ですが、なぜ盛んになったのでしょうか?その理由は、陸奥湾が地形的に適しているからです。東の下北半島・西の津軽半島・南の八甲田山系から流れる川が、ミネラル分を含んだ栄養豊富な水を供給しており、これがホタテの餌となるプランクトンが育ちやすい環境となっています。そのため、古くからホタテの生息が確認され、10〜20年に一度大量発生していたようです。

▲陸奥湾には、周辺の山々から栄養豊富な水が流れ込む。
青森活ホタテ専門店様HP(http://www.aomorihotate.jp)より。
更に昭和30年代にホタテの養殖が実現され、安定した漁が可能になると、今では青森市の沿岸漁業生産量および水揚げ金額の9割前後を占めている重要な特産品となっています。
夕食は、その青森特産のホタテを頂きに、郷土料理のお店「おさない(https://osanai.gorp.jp)」さんにお伺いしました!!ホタテラーメンにホタテ貝焼き味噌、ホタテ丼にホタテフライ…ホタテをふんだんに使った、青森の郷土料理を堪能できました!!

▲散々迷った挙句、ホタテラーメンを頼みました!!塩気は控えめだからこそ、ガツンと目の覚めるようなホタテのお出汁の香ばしさの一本で勝負しているラーメン。飲んだ後の締めで食べたら極上の気分やろうなぁと思った(もちろん飲んだ後でなくとも絶品のお味!!!)トッピングのホタテも特大で、新鮮さ特有の甘味もあって贅沢で幸せな気分でした。
③締めは、青森名産のシードル!
本日のラストは、JR東日本青森商業開発が2010年に開業した、A-FACTORYでシードルを頂きに行きます!青森発祥の品種「ふじ」を代表するりんごも、代表する名産として非常に有名ですが、ここでは、そのりんごを使ったシードルの生産と販売を同時に行なっており、試飲・購入ができるようになっています。

▲写真左手に見えてる建物が、A-FACTORY。青森駅から徒歩4分という立地の良さも魅力。モダンと伝統、使い心地が調和されたバランスは、国際的に評価されているインテリアデザイン会社のワンダーウォールが手掛けたとのこと。この建物は、2011年グッドデザイン賞受賞。
ここで、当ブログらしく少し脱線して、日本と青森におけるりんごの歴史を少し。(笑) 元来、日本には、平安時代に中国からもたらされて定着した和りんごがあり、中世には近江の戦国大名、浅井長政が、領内の寺から和りんごを献上されたこと対し、礼状を出したとの記録も残っています。ただし、あまり味が良かったとは言えないようで、主に薬、観賞用やお供物として流通していました。
現在広く流通している、西洋りんごが本格的に日本に入って来たのは、明治に入ってから。政府主導で全国各地にりんごの苗木が配布・試作され、明治10年に弘前で初めて結実した事を皮切りに、青森県各地で生産されるようになり、「ふじ」「つがる」をはじめとした品種が生み出され、2021年においては、りんごの県別国内生産量は全国ぶっちぎりの1位の463,000t(2位は長野県の135,400t)となっています。

▲A-FACTORYの中の様子。シードルの試飲と製造過程が見えるようになっています。また、青森各地の名店・名産も集められており、お土産を買うのにもってこいの場所。
さて、このA-FACTORYではなぜシードルが作られているかというと、上述のように日本で最もりんごが生産される青森県においては、味に遜色がない場合でも形や色の問題で廃棄されてしまう規格外品が非常に多くなっていることに対する問題意識がありました。そこで再利用・加工しシードルとして販売することで、フードロスの改善と青森りんごのさらなるイメージアップに繋げるという戦略があったそうです。
シードルの製造工程はこちらのHPをご覧ください!(https://www.jre-abc.com/wp/afactory/cidlefactory/)

▲シードルの試飲コーナー。1杯100〜600円で、8種類のシードルを飲み比べできます。シャンパンのような辛口からリンゴサイダーに近いような甘口まで幅広いバリエーションがあり、どれも非常に美味しく、甲乙つけ難かったです。。。ここは一つ奮発して、ぜひ全て飲んでみて比べて欲しいです。
以上が、新婚旅行1日目青森市での足跡でした!
青森の歴史は、厳しい自然との闘いの歴史であり、それゆえに前回記事で取り上げた三内丸山遺跡や奥州藤原氏、北畠顕家といったダイナミズム溢れる歴史や、今回記事で取り上げたねぶた祭りに代表されるエネルギッシュな文化が培われたと感じました。一方で、ホタテ漁や国産リンゴの開発など、その厳しさ故にもたらされる自然の恩恵を見事に活用してきた歴史もあり、そのしなやかさにはただただ畏敬の念を抱かざるを得ませんでした。
この記事を読んでくださった方々には是非とも青森市を訪れていただき、その歴史ダイナミズムとエネルギッシュな文化、自然の恵みを体感していただきたいです!
次回は、八戸市の旅について書きたいと思います!
【青森・函館旅行日記 1日目】青森市編①
ご無沙汰しております!!
手前味噌ではございますが、青森・函館に新婚旅行に行って参りましたので、その時の旅路を辿りながら記事を書いてみたいと思います!
本記事では、最初に行った町である青森市について書いていこうと思います。まずは、青森市の歴史から始めますので、旅行記から読まれたい方は、次回の記事へとお進みください!
1.古代の青森市
青森市の歴史は縄文時代に遡ります。有名な三内丸山遺跡は、国の特別指定史跡、また2021年には「北海道・北東北の縄文遺跡群」として世界遺産に指定されました。三内丸山遺跡は、縄文時代中期(約5900年前〜4200年前)に営まれた集落跡です。詳細は、5回目の記事に記載させていただければと思いますが、長期間にわたる暮らしの記録は、縄文時代の様子を知る上で貴重な価値を持つ、学術的に非常に重要な遺跡です。

②奥州藤原氏の台頭
平安時代に於いては、東北で起こった安倍氏・清原氏・大和朝廷の三つ巴の大乱である前九年の役・後三年の役を経て、奥州藤原氏が中央の政治には属さない独自の勢力を築きました。
2.中世の青森市
①鎌倉幕府(北条氏)の支配と崩壊
鎌倉時代に入ると、奥州藤原氏を滅亡させた鎌倉幕府の北条氏が奥州の大半を抑えることとなります。また、2代目執権北条義時は、安倍氏の末裔にあたる安藤氏(後の安東氏)を通して、奥州の統治にあたったようです。
しかし、鎌倉時代末期になると、勢力を拡大した安藤氏の内紛と、それにアイヌの反乱が重なった紛争(安藤氏の乱)を幕府は鎮圧することができず、元寇と並んで鎌倉幕府は衰退のきっかけとなった事件と言われています。
②浪岡北畠氏
室町時代になりこの地の支配者となったのは、浪岡北畠(なみおかきたばたけ)氏です。元々北畠氏は村上源氏の庶流で京都で活躍する貴族の家系でした。なぜ、北畠氏が奥州に勢力を築くことになったのか。その経緯をお話しするために、浪岡北畠氏の祖と言われる、南北朝時代の南朝側の若き名将、北畠顕家(きたばたけあきいえ)について、少し紹介したいと思います。

▲北畠顕家 Wikipediaより引用。政戦両略の名将にして美少年だったとのこと。
北畠顕家は、鎌倉時代末期に、村上源氏の流れを汲む公家の名門である北畠家に生まれました。この出自だけでなく、才覚にも恵まれていたため、若くして朝廷の重要な官職を歴任し、14歳という史上最年少の年齢で参議に抜擢されました。舞にも才能があったらしく、「花将軍」の異名もあったそうです。
④“花将軍“奥州へ
後醍醐天皇の覚えもめでたく、建武の新政において奥州の支配を任されることになります。当時若干15歳という若さ、しかも公家の出身にもかかわらず、武人としての才能も申し分なく、東北地方に根強かった北条氏の残党を見事鎮圧しました。また優れた統治手腕を発揮し、東北の武士達を配下に収めます。これが、北畠氏が奥州に根を下ろすことになったきっかけとなった出来事です。
因みに、この時従えていた重臣に、南部師行や結城宗広、伊達行朝といった、後の東北の戦国時代に名を馳せる大名家の祖先もいました。
⑤南北朝の騒乱と鬼神の如き活躍
南北朝の動乱が始まると顕家は、新田義貞(にったよしさだ)・楠木正成(くすのきまさしげ)に並ぶ南朝側の名将として大活躍します。後醍醐天皇に反旗を翻した足利尊氏が京都を占領した際には、東北から5万の兵力を率いて出陣しました。
この時の勢いが日本史上類を見ない凄まじさで、鎌倉で足利尊氏の息子足利義詮(よしあきら)を破り、間髪入れずに京都に進軍。新田義貞・楠木正成と連携して足利尊氏を破る快進撃を見せました。その勢いを前に足利尊氏は九州へと逃れざるを得ませんでした。
北畠顕家はこの間、足利家の諸将を打ち破りながら1日約50kmも進んだという記録が残っており、日本史上類を見ない規模と速度の行軍(比較として、本能寺の変に際し豊臣秀吉が行った中国大返しは1日約20km)として、名将としての名声を不動のものにしました。

⑥北畠顕家の最期
その後、多々良浜の戦い(現在の福岡市)に勝利し、九州で体制を立て直した足利尊氏が再び京都に巻き返して来ると、またしても軍を率いて京都に駆けつけます。しかし、その前に楠木正成は戦死、また新田義貞との連携が阻止され、孤立してしまいます。河内地方で孤軍奮闘するも力つき、堺で起きた石津の戦いで20歳の若さで討ち死にしてしまいました。
若くして文武に華々しい活躍を見せた北畠顕家は、日本史上屈指の名将と言っても差し支えないでしょう。顕家亡き後も、全国で各勢力が南朝側・北朝側に分かれて、50年以上もの間戦い続けることとなります。

▲明治に入り、顕家の後醍醐天皇に対する忠誠が再評価され、阿倍野神社に父親房と共に祀られている。
⑦室町・戦国の青森市
その後、東北本国の浪岡北畠氏は、南北朝の騒乱の中で勢力を衰退させながらも、津軽に浪岡城(青森市浪岡)を築城し、南部氏や安東氏など有力大名との關係によりその後も存続しました。天皇家に連なる名門公家の出身の家柄であることから、京都との繋がり強く、浪岡には貴族文化が入り「北の御所」と呼ばれました。このように、権威的存在として、戦国時代を通して津軽地方を中心に特別な地位を保ちました。これが浪岡北畠氏の誕生の経緯です。
しかし、戦国末期に、下剋上によって南部家からの独立を果たした津軽為信(つがるためのぶ)によって、ついに滅ぼされてしまうことになります。そして、この南部氏と津軽氏の関係が、後の青森港の誕生に大きく関係してくることになるのです。


▲戦国末期の南部家と独立を果たした津軽氏の領域。
3.近世の青森市
江戸時代においては、青森市は弘前藩の一都市として、津軽氏の治めるところとなります。そして、2代目藩主津軽信枚(つがるのぶひら)の代には、森山弥七郎(もりやまやしちろう)に命じて、江戸に津軽米を輸送する拠点として青森に港町が整備されることとなります。
この事業にはもう一つの狙いがありました。それはこの地域にもともとあった油川湊(現青森市油川)の権益を奪うことにありました。既述の通り、そもそも津軽藩の成り立ちは、初代津軽為信が主君である南部氏の内紛に乗じて反旗を翻し独立したという経緯があります。この地域の港町である油川には、南部時代からの商人達が多く、なかなか津軽家に従わなかったと言われています。
その対策として、新たに青森湊を建設し津軽家主導の元運営されることとなりました。この青森湊の完成以降、青森は酒田(秋田藩)〜江戸を結ぶ東廻り航路に参入し津軽米を江戸に運ぶ重要な役割を担い繁栄します。

▲江戸時代の商業を発展させた海上交易路
水の文化センター様HPより。https://www.mizu.gr.jp/kikanshi/no01/02.html
4.近代の青森市
さて、幕末に浦賀・横浜にやってきた黒船は、泰平の世を謳歌していた日本に外国の脅威が迫っている現実を突きつけました。そしてそのことは、函館戦争を経験した明治政府に、北海道の防備と開拓を進めることと同時に、青森の北海道への中継港としての重要性を再認識させることとなります。これが、青森市が当時弘前県の県庁所在地として認められる要因になったと言われています。
明治以降の魚介類の輸入や東北・奥羽本線・青函連絡船の開通は、さらに青森港を発展させることとなりました。1988年の青函トンネル開通を機に青函連絡船は運行終了となったものの、北海道との車両輸送、LPGや石油の輸入など現在も重要な役割を担っています。

▲青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸。(4回目の記事に書きたいと思います。)
以上まで、青森市の歴史をところどころ脱線しつつ(笑)、書かせていただきました!青森市の地理的・歴史的な重要性や魅力を、少しでもお伝えすることができたのなら、大変嬉しいです。
【商人旅】〜会津商人篇④〜 会津の旅の足跡(後編)
今まで3回に渡って書いてきた会津若松編ですが、とうとう今回で最後になります!!
1.満田家で郷土料理
3日目は、朝から七日町通りにある満田屋さんに並んで、ブランチに郷土料理の味噌田楽をいただきました!この満田屋さんは、幕末(天保5年)創業の味噌専門店です。郷土料理のしんごろう餅や身かきにしん、里芋などに3種類の秘伝の味噌だれを塗り炭火で丁寧に焼かれた贅沢な田楽がいただけます。




2.飯盛山と白虎隊
①飯盛山の見どころ
朝のお腹が満たされたところで、飯盛山に向けてドライブしました。飯盛山はかの有名な、白虎隊が会津戦争で自刃した場所です。
近くの駐車場に車を止めると、地元の商魂逞しいおじ様おば様たちお土産の紹介を受けつつ(笑)売店街を抜け 、急峻な石段にたどり着きました。
山頂に登ると、白虎隊にまつわる記念碑や像を中心に幾つかの見所があります。


飯盛山のもう一つの名所として、さざえ堂があります。正式名称は円通三匝堂(えんつうさんそうどう)と言います。上りと下りの道が別れていて、参拝者たちがすれ違うことがないような珍しい設計がされています。

②白虎隊の悲劇
ここで、白虎隊の悲劇が起きた経緯を簡単に説明します。幕末の動乱期、江戸幕府は江戸城の開城を以って実質的に滅亡し、代わって明治政府が樹立しました。しかし、北越・東北地方を中心に旧幕府側の勢力が奥羽越列藩同盟(おおうえつれっぱんどうめい)を結成し、明治政府との戦いを継続していました。会津戦争はこの東北地方の戦いでの一局面となります。
会津軍は新政府軍に対し、当初から軍備も物量も大きく差を開けられており、終始、圧倒的不利な戦いを強いられました。白虎隊の悲劇が起きる少し前、この時の主な会津藩の戦線は、越後口(新潟方面)・日光口(栃木方面)・石筵口(福島県東部)でした。このうち石筵(いしむしろ)口には、大鳥圭介の伝習隊や土方歳三の新撰組といった精鋭を配置するも、板垣退助率いる9倍近い新政府軍相手に敵わず僅か1日で敗走する結果となりました。

この敗戦は、会津藩にとっては想定外に早すぎるもので、何とかして新政府軍を足止としようとしますが、その勢いの前になす術もなく負け続けてしまいます。そんな状況の中、会津軍は明治政府軍に一矢報いるべく、戸ノ口原で防御陣地を築いて最後の防衛戦を狙いました。
白虎隊は、16・17歳の武家の少年兵で構成され、本来は予備戦力としての位置付けの部隊でしたが、このような絶望的な状況で戸野口原の戦闘に参加することになりました。当然ながら戦局の挽回からは程遠く、懸命に戦うも壊滅し飯盛山に逃げ込みます。もはや、彼らの最後の希望は、主君である松平容保が守る会津若松城での戦いでした。
飯盛山で起きた白虎隊の悲劇とは、この戦いで飯盛山に逃げ延びた白虎隊の隊員が、山頂から煙の登る会津若松城を見て、会津の運命ももはやこれまでとこの飯盛山で自刃する道を選んだ出来事でした。

江戸時代では、もう元服を済ませた侍とはいえ、まだあどけなさが残っていたであろう彼らの悲劇を思うと、胸に苦しく響くものがあります。時代や社会、大人たちの利害に翻弄されながらも、必死に生き、散っていった彼らの姿を忘れずにいることは、時代の変わり目における大人達の意地や利害や信念のために、後に続く世代を犠牲にしてはいけないという教訓として大切にしなければいけないと思います。
時代を進めるにも止めるにも、その目的とは、自分たちの世代だけではなく後世に財産を伝えるためでなくてはいけないと思います。私もブログを書くにあたり、いつの日かそういった歴史の遺産を語り継ぐことができるような、そんなクオリティのある記事を書けるようになりたいと願います。
3.御薬園
次に、会津三名園に数えられる有名な日本庭園の一つ、御薬園に向かいました。
御薬園は、病を患った病人にこの地にあった泉の水を与え治癒させた伝説がつたえられており、蘆名氏が15世紀に入り神聖な土地として別荘を建てたことが始まりです。
その後戦国の乱世の中廃れていた時期がありましたが、江戸時代に入り初代藩主保科正之が再建しました。2代藩主正経・3代藩主正容の時代に農民を疫病から救いたいという思いから薬草園が整備され、藩主導で薬の研究が行われました。
この御薬園は、蘆名家に遡る会津の歴史を土台に、会津松平家の理念とも言える領民の生活安定の願いが表現された、重要な場所でもあると言えるでしょう。

この薬草園で、正容の時代に導入された朝鮮人参は、薬草としての効能もさることながら、約120年後に起きる天明の飢饉で大打撃を受けた藩財政を立て直す財源として、以前の記事にも取り上げた、名家老の田中玄宰(たなかはるなか)が着目し官民一体で藩の特産物として育成されました。

御薬園では、現在も会津特産の薬用人参をはじめ400種類のハーブや植物が育てられています。江戸時代に当時の人達が領民のために薬草を集め薬を作る姿が目に浮かぶようでした。お土産店では、御薬園で育てられた植物で作られた健康茶が販売されています!
この御薬園は、会津戦争においては新政府軍に接収され診療所となったため戦火を逃れました。戦後長尾和俊に代表される会津の豪商たちが私財を投げ打って新政府から買い戻し、松平家に献上されました。明治時代に松平容保も一時期この場所で過ごしたと伝わっています。大正ロマンの代表的な歌人、与謝野晶子も訪れたそうです。
続いて、会津を代表する会津塗の老舗、白木屋漆器店さんへ。その起源は17世紀中頃に、加藤氏の時代に会津に来て、木綿を扱う商人だったとのこと。

18世紀に入り漆器業を手がけ、江戸だけではなく上方にまで販路を広げました。17世紀初頭に保科正之が行なった殖産興業政策とも関係あるのではと思えます!戊辰戦争の戦火の中も生き延び、明治に入ると会津塗の復興に尽力され、有名なパリ万博にも出店されたとのことです。お店をお伺いすると、今尚受け継がれる伝統的な会津塗の品々と多くの展示資料があり、現在でも会津塗の普及に貢献されています。僭越ながらこれぞ老舗の名店!と申し上げたくなるような風格を備えていると思いました!
白木屋漆器店の素敵な商品の数々はこちらのリンクに掲載されています。
また、建物の詳細情報は、こちらのリンク参照ください。
5.渋川問屋
最後に、会津の旅のフィナーレとして、会津若松の郷土料理の専門店、渋川問屋でディナーをいただくことにしました!!
渋川問屋は、会津若松のメインストリート、七日町通りに明治時代に、北前船から運び込まれる海産物を干物にして会津の食卓に提供する海産物問屋として繁盛したそうで、ニシンの干物の東日本の相場に強い影響を持っていたそうです。

会津随一の海鮮物問屋として繁栄しましたが、昭和には一家の長男であった渋川善助が二・二六事件に連座するなど、激動の時代に巻き込まれました。現在は、旅館と懐石料理のお店として会津でも人気スポットなっていますが、日本の各社社会を憂いた善助の育った部屋は、「憂国の間」として今も残されており、松本清張や三島由紀夫も訪れているそう。(詳細はこちらのリンクをご参照ください。)
今回は、宿泊はできませんでしたが、会津での最後のディナーということで、コースメニュー(会津会席膳)を注文しました!!伝統的なお料理に舌鼓を打ちつつ、明治・大正の姿のまま保存されたレトロな建築空間が、旅情を誘う素敵なひと時を過ごしました!


2膳目は、にしんの山椒漬けと、にしんの昆布締め。にしん料理も会津の代表的な郷土料理。山椒締めはにしんの臭みがなく、山椒の香りは仄かにする味付け。歯ごたえがあり噛めば噛むほどにしんの出汁が口に広がる。昆布締めは、昆布に巻いて砂糖醤油酒等で味付けしている模様。濃いめの味付けの中にも昆布とにしんの味がしっかり活きていて、日本酒にピッタリ!








6.最後に
これでとうとう、会津の旅の記事が終わりになります!本当はもっと行きたかった場所や書きたかった場所がたくさんあるのですが、今回の記事は一旦ここまでとし、きっといつの日か会津の地を改めて訪れる際の楽しみにしたいと思います。
会津を旅する中で、激動の時代にあって信念を貫いたことに対する先人達への誇りがあり、それを大事にすることで育まれた歴史や文化は、掛け替えのない財産となっていると感じました。

これはあくまで個人的な意見ですが、世界史と日本史の大きな違いの一つは、世界史は勝者の歴史である一方、日本史は敗者の歴史も等しく慈しむ所にあると思います。アジアやヨーロッパの歴史に於いては、前の支配者の築いた財産を、後の支配者が徹底的に破棄することが散見されますが、日本においては源平合戦や戊辰戦争に代表されるように、勝者・敗者両方の歴史を大切にする傾向があり、そうすることで育まれた日本の歴史はとても濃密で、深みのある物語になっていると思います。
昨今、SDG‘sの重要性が語られることが多いですが、様々な町・人・製品に対して、歴史は付加価値をつけてくれる効果があると思っています。この付加価値は、資源を消費したり廃棄物を出すことなく生み出すことができ、非常に“SDG‘sな“価値の生み出し方だと言えます。
先述したとおり、日本には勝者も敗者も分け隔てなく愛情を向ける文化があり、それにより育まれた歴史や文化には他国に負けない特別な価値があると思います。私もこのブログを書く中で、少しでもそういった歴史の楽しさ、美しさ、魅力を伝えることができればと気持ちを新たにした、そんな旅となりました。
余談:その時世界では
御薬園が、会津3代目藩主松平正容によって造園された17世紀末、北欧では北方同盟が結ばれました。当時バルト海沿岸の全域を支配下に置き、バルト帝国と呼ばれるほどの圧倒的な勢力を誇っていたスウェーデンに対し、ロシア・ポーランド・デンマークが同盟を結び、1700年から約20年に渡り繰り広げられる大北方戦争のきっかけとなります。
「北方の流星王」の異名を取るスウェーデン王カール12世は、序盤こそ素早い機動戦で先手を取りデンマーク・ポーランドを屈服させるものの、ポルタヴァの戦いで好敵手と評されるロシアのピョートル大帝に敗れた後は勢いを失い、台頭著しいプロイセンにも参戦されるなど、最終的には敗戦という結果に終わります。結果、ロシアが東欧・北欧に於ける覇権国の地位を確立。この地位と東ローマ帝国皇帝家との血縁と共に、ロシア王家は名実ともに「皇帝」の称号を得て、ロシア帝国が成立することとなりました。
ロシア帝国は、この頃までに既に太平洋側までその国土を拡大させていましたが、当時絶頂期にあった清朝とのネルチンスク条約(1689年)においてアジアでの不凍港の獲得の失敗という結果になりました。この事と、先述の北方大戦争におけるヨーロッパでの成功から、ロシア帝国の不凍港の獲得を目指した南下政策の矛先は、スウェーデンという旧覇権国を打破したヨーロッパ方面、第二次ウィーン包囲に失敗し衰退期に入っていたオスマン帝国との抗争に向かうことになります。
これらの情勢は、日本とロシア帝国の接触を150年近く遠ざけることになります。再びロシア帝国がアジアに南下政策の矛先を向けるのは、清朝が衰退期に向かう19世紀の中頃。アイグン条約(1868年)・北京条約(1870年)によって念願の不凍港であるウラジオストクを獲得します。日本では戊辰戦争の最中にあり、アイグン条約が結ばれた丁度その頃、会津戦争に向けて着々と明治政府軍が進軍している最中のことでした。
【商人旅】神戸の街の「和と洋」・「古きと新しき」が交わる場所、相楽園
今回は、神戸市民から100年以上もの間親しまれ続け、神戸市の歴史と発展を見守り続けてきた歴史ある日本庭園、相楽園を取り上げたいと思います。
皆様は、神戸の街にどのようなイメージをお持ちでしょうか?ファッション、異人館、お洒落なカフェや雑貨屋さんetc… 実は、この相楽園を造営した小寺泰次郎(こでらたいじろう)は、この関西を代表するオシャレの街、神戸市の発展に大きく貢献した重要人物なのです!そんな小寺泰次郎と、彼と共に神戸の街の発展を見守ってきた相楽園の歴史を紹介いたします!

①小寺家のルーツ
相楽園は、小寺泰治郎氏の邸宅として、1885年(明治18年)頃に造営されました。小寺家は、戦後最初の神戸市長である小寺謙吉(泰次郎の子)を輩出するなど、神戸を代表する名士でしたが、元は三田藩(現在の兵庫県三田市)の藩主であった九鬼(くき)家に仕えた下級武士の家でした。
九鬼家といえば、戦国時代に織田信長の元でその名を轟かせた強力な九鬼水軍で有名ですが、江戸時代に入っても、幕府の礼式を取り仕切る要職として外様大名としては特別な地位にいました。

②小寺泰次郎の活躍
そして時は幕末、日本中が尊王攘夷と開国佐幕に思想が二分していた激動の時代でした。その中にあって、最後の三田藩主である九鬼隆義(くきたかよし)は、三田藩の軍備の西欧化など、近代化を断行しました。この時に、下級藩士の身分から取り立てられ活躍した人物が2人いました。そのうち1人が白州退蔵(しらすたいぞう)、そしてもう1人が小寺泰次郎だったのです。

▲出典:NPO法人歴史文化財ネットワークさんだ。左から九鬼隆義、白洲退蔵、小寺泰次郎。志摩三商会設立のこの3人は神戸の街の発展に大きく貢献した。因みに、白洲退蔵は終戦直後の日本の大政治家、白洲次郎の祖父にあたる。
明治に入ると、九鬼隆義・白洲退蔵・小寺泰次郎は、困窮する旧三田藩の武士を救うために、「志摩三商会」という貿易会社を神戸で設立。食料品・雑貨・薬などの貿易で成功を収めました。
志摩三商会の成功や、不動産・金融業で一躍大富豪となった小寺泰次郎は、その資金を元手に、予てから国際港としての素質を見出していた神戸の発展に多額の投資を行いました。現在の元町・三ノ宮の都市開発、神戸女学院の前身である女子寄宿学校の設立にも関わっています。小寺泰次郎はこの相楽園の地から、現在に至る神戸の街の発展を見据えていたことでしょう。
③その後の相楽園
さて、その後の相楽園は、1941年に小寺家から神戸市に引き渡され、中国の古書「易経」の一節「和悦相楽(和して悦び相楽しむ)」から引用して相楽園と命名され、市営公園として一般公開されることになりました。1945年の神戸大空襲により被害を受けましたが、旧小寺家厩舎(国の重要文化財)や灯篭や門・塀などが遺り、貴重な文化遺産として神戸の歴史の1ページを現在に伝えています。
その文化的価値から、日本の文化財保護法に基づく登録記念物として、最初の登録物件となりました。

戦後、神戸市の迎賓館として旧相楽園会館が1963年に完成し、55年間にわたり人々の交流の場として親しまれてきました。そして、2018年、より広くたくさんの人々にその魅力を発信するために、旧相楽園会館を活用する企業コンペが行われ、旧相楽園会館は、ウエディングやイベント、レストランやカフェとして利用される、THE SORAKUENとして生まれ変わることになりました。




相楽園を訪れてみて、併設の日本庭園や異人館と調和しつつ、和モダンでスタイリッシュな粧い、そして、カフェやレストランで味わうお料理も、”伝統tradition x 革新innovation”のコンセプトを美しく体現していると感じました。それが江戸までの日本の歴史と新たな西洋文化の融合を果たした大正ロマンのような雰囲気を醸し出していると感じます!!
神戸の街の真ん中にありながら、暫し都会の喧騒や日常を忘れさせてくれるこの相楽園で、平和でロマン溢れるひと時を過ごしてみてはいかがでしょうか?!
余談:その時世界では
小寺泰次郎によって、相楽園が造営され、神戸の街が発展を見せはじめていた19世紀後半、ヨーロッパはその繁栄が成熟期に差し掛かっていました。フランスでは、ゴッホやゴーギャン、セザンヌをはじめとしたフランスのポスト印象派の画家たちが活躍をし、リュミエール兄弟によって映画が発明されました。
個人的には、このようなヨーロッパの文化が成熟を表現している一方で、産業革命における貧富の差の拡大、帝国主義による領土拡張の限界、ナショナリズムの高揚や勢力均衡の世界情勢など閉塞感を孕んでいると感じます。この一見華やかな中に忍び寄る影のような寂しさを感じるのが、この時代の物悲しげな魅力であると感じます。
この19世紀後半には、戦争と動乱の20世紀の影も忍び寄ってきていました。ドイツでは首相のビスマルクが失脚。ビスマルク体制と言われ、ヨーロッパに安定と文化的成熟をもたらしていた勢力均衡状態が瓦解し始めます。また、アフリカにおける英仏の利権対立が頂点となったファショダ事件が発生しましたが、ここで勢力争いに折り合いをつけた両国は接近をし、急速に台頭するドイツへの警戒を強めていくことになります。
【商人旅】〜会津商人篇③〜 会津の旅の足跡(前編)
今回は、前回記事での宣言通り、白河での観光を終えてから会津若松への旅について語って行こうと思います。(白河の観光はこちらのリンクをご覧ください!)
またまた記事が長くなってしまいますので、2回に分けてお伝えします。長くなってしまい恐縮ですが、どうぞお付き合いください。m(_ _)m
・前編(商人巡り)
1日目:大内宿・会津珈琲倶楽部・割烹田季野
2日目:まなべこ・福西本店・清水屋跡・なかじま(カツ丼)・会津若松城
・後編(歴史定番スポットとグルメ)
3日目:満田屋・飯盛山・御薬園・白木屋・會津酒楽館・渋川問屋
1.一日目
①大内宿
白河を13時ごろ出て、会津若松に続く道を2時間ほど進んだ中間地点に、大内宿(おおうちじゅく)という江戸時代に栄えた宿場町が遺っており、立ち寄りました。

この地は、鎌倉〜戦国時代まで、藤原氏(秀郷の子孫)の子孫である長沼氏の支配下にありました。しかし、戦国時代に関東公方家と室町幕府の内乱である享徳の乱に巻き込まれた際に、滅亡してしまいます。
江戸時代に入ると会津藩領に組み込まれ、会津から江戸へ向かう道中に位置する宿場町として繁栄します。江戸時代は日光地震や戊辰戦争も生き抜いた大内宿ですが、明治維新に入ると、新たな街道・鉄道の整備の中で近代化の波から取り残されてしまいました。しかし、そのことが却って、見事な茅葺き屋根の伝統的な町並みが残る要因となったのです。1981年に、重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。

大内宿に着くと、まず山形屋さんで遅めの昼食(ねぎ蕎麦・イワナの塩焼き)を頂きました。


続いて大内宿町並み展示館に行き、大内宿の歴史・昔の生活用品・茅葺き屋根の手入れ方法など、様々な説明を学ぶことができました。決して贅沢とは言えない生活様式の中に、豪雪地域の厳しい自然環境の中でもたくましく生きていた人々の息遣いや生活感を感じられるような、臨場感あふれる展示でした!


②会津到着!会津珈琲倶楽部でコーヒーブレイク & 田季野輪箱飯で晩御飯
会津若松の町に入ると、いかにも城下町というような、同じようなやや狭めの幅でジグザグした道と、同じような広さの土地に建った建物が並ぶ街並みになります。(この独特の街並みの成り立ちについては前回記事ご参照ください!)



お昼が遅かったこともあり、お腹が空くまで會津珈琲倶楽部にて、素敵なコーヒーで一服。カフェバーのようなシックでおしゃれな雰囲気で戴く一杯は、旅行気分を盛り上げてくれます!そして、ここのBGMが、1950〜60年代の古き良きアメリカの音楽で思わず聴き入ってしまい、その場で旅の想い出にダウンロードしました。笑

さて、18時になりお腹の減りもいい具合になってきたところで、会津での最初の晩御飯に向かうことにしました!向かったのは、会津の歴史と文化を味で体感できるお店、ということで、会津郷土料理の輪箱飯の専門店、田季野輪箱飯さんです!店構えから歴史と拘りを感じることができる、重厚感溢れる料亭です!www.takino.jp


この輪箱飯は、噛みごたえのある会津若松の文化と歴史を象徴しているようで、これからの旅に向けてワクワクが増す素敵な晩御飯でした(^ ^)
③会津若松市歴史資料センター「まなべこ」

今回の会津若松の旅の本番はここから始まったと言っても過言ではありません。旅の2日目のスタートは、会津若松市歴史資料センター「まなべこ」様からです!
この資料館では、会津商人の歴史を中心に、郷土の特産品・偉人や江戸時代の町割りなど、貴重な資料が数多く展示されています。また、会津観光情報もあり、旅の計画を立てる為にも是非とも訪れて頂きたい場所です!!
資料の展示は一つ一つがカラフルでメリハリも効いていて、とても見やすい内容となっています。歴史に詳しい人もそうでない人も、会津について楽しんで学べる素敵な資料館だと思いました!
まなべこ館内のご案内 | 会津若松市歴史資料センター まなべこ


現在もお土産やお食事処が並ぶ七日町の、商家の店舗一覧が見れます。全国各地の地名に由来する屋号が多く見え、各地の商人が会津の地を有力な売り先として評価していたものと思います。当時の広告の役割のあった絵札はとても華やかで見応えがあります!また、右奥のパネルには、会津の偉人達の紹介があります。

今回は、会津商人を訪ねるというテーマで、会津若松を訪れたのですが、会津の商業について、貴重な情報を数多く伝えていただき、実りの多い取材となりました!!
更に会津商人について深く学ぶために、その足跡が伺える歴史スポットとして代表格といっても過言ではない、福西本店様に向かいます!!
④福西本店
福西家は、会津において、江戸時代は綿古着を取扱う商家として活躍し、明治時代には問屋業・味噌醤油・漆器にも幅を広げ、最盛期には会津地方の銀行・鉄道・水力発電業に強い影響力を持つ随一の豪商となりました。

この福西家が会津に来ることになった歴史的背景は大きく二つあるといわれています。一つ目は、戦国〜江戸初期に会津を支配した蒲生家とのコネクションです。福西家のルーツは、大和国(現在の奈良県)の宇陀郡福西(うだぐんふくにし)にあったとされます。同地は、古くから近江日野との繋がりが深い地域で、蒲生家とも浅からぬ縁があったと言われています。検断として大きな力を持っていた簗田家から、当時の城下の一等地に大きな間口を与えられるという破格の扱いもこれを裏付けていると思われます。
因みに、福西家は室町時代に権勢を誇った播磨守護の赤松氏の中に、大和国に領地を与えられ福西の姓を名乗った一族があり、その末裔と言われています。

二つ目は、初代福西善照が仕えていた堺の商家の藤井家が、会津若松へ支店を出すにあたり任されたことが発端とされています。この藤井家は、古着を扱う商家で、かの有名な鴻池家とも張り合えるほどの商勢があったと文献に記述されているそうです。
幕末の戦火に巻き込まれ、会津藩へ用立てた資金の貸し倒れや、略奪の被害で苦境に陥りますが、明治〜大正にかけて7代妻イネ・8代善運・8台妻フサの元で見事立て直し、一族の多くを地元の有力な商家を継がせるなど、最盛期の下地を築きます。現在にも残っている風格ある店構えは、この時代に作られたものです。
そして、9代の善真は、会津銀行の設立や鉄道・電力業にも手を伸ばすなど、福西家の最盛期を現出し、会津有数の豪商となります。
しかし、10代善徳以降は芸術方面へ出費がかさみ、それ以降の店主も早くに亡くなるなど、商勢が再び戻ることもなく、戦後日本の社会変動に適応できないまま、会津若松まちづくり(株)に家を譲り渡すこととなりました。




5.なかじま(カツ丼)・清水屋跡・会津若松城
さて、取材をしっかりさせて頂き、お腹が減ったところで、この日の昼食は、会津若松のソウルフード、煮込みソースカツ丼!大正〜戦後にかけて東京の洋食文化を取り入れ、ソースで煮込むアレンジを加えて完成したのだそう。
今回は、福西本店の方にオススメ頂いた、なかじま、というお店でいただきました!こういうのは、地元の方にお聞きするのが一番ですね!!

腹ごしらえを済ませると、満を持して会津若松城(鶴ヶ城)に向かいます!
鶴ヶ城は今までの記事にも書いてきましたが、会津の誇る難攻不落の名城です!元は蘆名氏の居城、黒川城として14世紀から会津の中心地として栄えていました。蒲生氏郷が会津の地に来て改築し、加藤家の時代に現在の姿になったとのことです。

7層の壮麗な姿で権威の象徴としての役割だけでなく、会津戦争においては新政府軍の猛攻にも1ヶ月耐えた、文武を兼ね備えた日本屈指の名城です!
明治に入って取り壊されましたが、その後、人々の寄付により昭和40年に蘇り、平成23年には幕末時代の赤瓦を再現した姿になりました。そして、最上階では、会津の城下町を一望できる絶景が見えます!!


さて、今回の記事は、会津旅行の1〜2日目をまとめました!会津商人にスポットを当てた旅にしようと計画を立てていたので、計画的に巡ることができたと思います。
まなべこ様で展示されていた、藩校の設立に会津商人が携わったエピソードや、福西本店の地域に根ざした商売の歴史などを見ていく中で、今まで見てきた地方の商人たちの中でも、特に会津商人は地元への忠誠心や愛着が強い商人であると感じました。
(その歴史的背景については、前の記事にても考察してみましたので、是非読んでいただければと存じます!)
この日は、まなべこ様と、福西本店様を立て続けに取材にお伺いしたのですが、非常に密度の濃い取材となりました。このような無名の駆け出しブロガーのためにお時間を取っていただき、大変有り難い限りでした!本当に有難うございます。
次の記事は、会津編の最終回、旅の3〜4日目の内容になります。乞うご期待ください!!
余談:その時世界では
会津若松城が、明治新政府軍と会津藩の激戦となっていた1868年、アメリカでは米国憲法修正第14条が批准されました。南北戦争が集結して3年が経ち、元奴隷の権利を確保することを意図して作られた条項となります。しかし、南部の社会では引き続き白人とそれ以外の人種の隔離が維持され、KKKなどを生み出す土壌となり続けました。これらの問題の改善は、1950年代のキング牧師の活動に代表される公民権運動までなかなか前進することがありませんでした。
【商人旅】〜会津商人篇②〜 蒲生氏郷と保科正之、そして藤樹学
随分と時間が開いてしまいましたが、いよいよ会津若松についての記事に入ります!調べれば調べるほど、会津の歴史は興味深く、ついつい記事が長くなってしまったので、会津篇は、2回に分けて、下記の流れで追っていきたいと思います。
今回記事
1.戦国から江戸時代への橋渡しをした、蒲生氏郷(がもううじさと)
2.会津松平家225年間を支える屋台骨を立てた、保科正之(ほしなまさゆき)
次回以降(会津の旅の足跡(前編)・会津の旅の足跡(後編))
・会津の商人・歴史スポット記録
・会津のグルメスポット記録
1.戦国から江戸時代への橋渡しをした、蒲生氏郷(がもううじさと)
会津藩の歴史を語る上で、豊臣天下の時代に会津を治めた蒲生氏郷の治世から話を始めたいと思います。
蒲生氏郷は、戦国末期の近江日野出身で、最初は六角氏に仕えていましたが、父が近江を攻略した織田信長に降り、氏郷は人質として信長の側に付き従うことになります。当時から、文武ともに並々ならぬ才覚を見せていたようで、織田家中の次世代を担う逸材として期待されていたようです。
氏郷は織田信長の元で政治手腕を学んだと思われます。後に氏郷35歳の時、天下を統一した豊臣秀吉の命により、会津の地を治めた際の鮮やかな政治手腕は、安土城を築くことでその威光を天下に知らしめ、楽市楽座を奨励し経済の活性化を目指した織田信長のそれと非常に似ていると感じます。氏郷は、40歳の若さでこの世を去ることになりますが、僅か5年の会津での治世の間に行なった政策は、現在の会津若松の基礎を築いたものとして、非常に高い評価を受けています。
では、そんな蒲生氏郷の統治を、会津商人の関係にも触れながら、纏めたいと思います。
①鶴ヶ城の大改築
蒲生氏郷は、秀吉の命を受けて会津に着任してから僅か1年余りの間に、かつての蘆名氏時代の姿のまま受け継がれていた黒川城の大改築を行います。ここに姿を現したのは、7層の天守を持つ本格的な近世城郭で、蒲生家の家紋に因んで鶴ヶ城と改名されました。また、地名もそれまでの“黒川”から、氏郷の郷里に因んで、“若松”に変えました。
天守閣を持つ城は、戦国末期からの主流となりつつあった城の形態で、軍事よりもシンボルとして求心力を高める政治的な目的が強いとされています。会津の地に、「我こそは新たな支配者である!」と宣言することで、リーダーシップを発揮する下地を整えたのです。

②城下町の拡大
蘆名時代に築かれた城郭は、手狭になっていたため、城下町の建設にも乗り出します。まず、車川を利用した外堀を築きました。そして、外堀の内側にあった神社や寺を外に出し、代わりに家臣を内に住まわせます。更に、外堀の外に庶民を住まわせることで、街が発展する余地を生み出し、要所に寺社や寺を配置するなど、現代に残る会津の町を整備しました。

③商工業の奨励
上述の城と街を整えると、今度は商業の振興にその辣腕を振るいます。
まずは、経済システムの構築です。十楽と呼ばれる、楽市・楽座を発展させた商業政策を行い、毎月、1〜10日それぞれの日を定めて6箇所で市を開くこととしました。また、人材育成にも力を入れます。蒲生氏郷の故郷である近江日野から、優れた商売センスを持つ近江商人を呼び寄せ、彼らの販売ノウハウを活かした、商業の発展を目指しました。例えば、倉田家は、氏郷の招聘で会津の地にやってきたという説が有力で、「四検断(後述)」の一角を占める豪商となりました。
その一方で、会津では、簗田家・坂内家、小池家をはじめとする、蘆名時代からの世襲の商人が強い力を持っていて、地域の商人たちを束ねていました。氏郷は、その伝統的地位を温存するだけでなく、連れてきた近江商人達には、これからは会津商人と名乗るように命じるなど、まさに温故知新の精神で、地元の人々との融和にも心を砕きました。
ここに出てきた、簗田・坂内・小池・倉田の豪商家は、江戸時代を通して「四町検断」の役職を世襲し、税収・訴訟・戸籍の管理・政令の伝達を取り仕切りました。このように会津商人は、官民のつなぎ役として会津の行政に於いて重要な役割を担いました。

④産業の育成
蒲生氏郷が着目し、素地を作った代表的な特産品として、会津塗・会津絵蝋燭・日本酒が挙げられます。
元々、蘆名氏の時代に漆の樹の栽培が奨励され、樹液からは漆器、実からは蝋燭が作られる様になっていました。氏郷はこれに注目しました。前述した通り氏郷の出身地は近江であり、その商勢を振るいつつあった近江商人に強いコネクションを持っていました。そして、近江商人の主力商品にも、漆器や蝋燭があったのです。氏郷は、近江から高い技術を持つ漆器や蝋燭の職人を呼び寄せ、現代に続く会津塗と会津絵蝋燭の素地を生み出しました。また、日本酒についても、同じく近江から杜氏を招く事で、当時は上方でしかまともに生産されなかった日本酒の生産に力を入れました。
この様に氏郷は、政治・市場機能を整えた上で、特産品を作る事で会津の経済力の基盤を作る事を目指したのです。
会津塗(出典:白木屋漆器店様HP)1800年代初頭に完成したと言われる会津の伝統的な絵で、会津絵と呼ばれる。桧垣、松竹梅、破魔矢などの文様で構成され、松は常に変わらぬ平安、竹は風雪にも耐えうる力、梅は寒さの中で放つ清らかな香りを表現し縁起物の破魔矢と合わせることで、人生の門出や一期一会を大切にする精神をが現されている。
会津絵ろうそく祭り(引用:会津若松観光ナビ様)会津若松の冬の風物詩で、鶴ケ城や御薬園など、会津の各所で計約1万本もの会津絵ろうそくが灯され、暖かい光に包まれるとのこと。
蒲生氏郷の政策をまとめると、ハード面(城郭・城下町の整備)、ソフト面(近江商人の招聘・既存の商人の活用、市場の制度)を整え、製品(会津塗・会津絵蝋燭・日本酒)を生み出して販売を奨励するという、現代の企業にも近い経営感覚を持ち合わせた、理論的かつ革新的な大名であったと言えると思います。
この蒲生氏郷が築いた基礎があったからこそ、会津は戦国末期〜江戸初期にかけての激動の時代の荒波を耐える事ができたのかもしれません。
2.会津藩松平家225年を支える支柱を立てた、保科正之(ほしなまさゆき)
その後、会津を治めた大名は、戦国〜江戸初期の激動の影響を受けたのか、長続きしませんでした。君主を上杉氏・蒲生氏(第2次)・加藤氏と頻繁に藩主が変わった後、日本史上屈指の名君と名高い、保科正之によってようやく落ち着きます。(会津松平家始祖)
保科正之は、江戸幕府2代目将軍秀忠と後北条氏旧臣の娘との間に、ご落胤として生まれました。その出自のため、幼少期は存在を隠され保科氏の養子になっていました。
その後、偶然にその存在を知った後の3代目将軍家光と対面し、正之は大いに気に入られたそうです。家光が将軍になってからも、真面目で有能な正之は絶大なる信頼を寄せられ破格の待遇を受けました。家光亡き後も、4代目将軍家綱の後見人として、幕府の政治の中枢を担い、災害・公共事業などに尽力して、幕府それまでの武断政治から文治政治への転換を実現し、江戸幕府265年の平和の礎を築きました。その功績から、松平姓を許され会津松平家の祖となっています。
そんな正之が任された会津の地は、江戸から遠く離れた東北の地、特に北の最大の外様大名、仙台藩伊達家を睨む地理的要衝にあり、幕府からの信頼の厚さが伺えます。ここでは、保科正之が会津の地で行なった政策を会津商人との関係についても触れながら纏めます。
①政治体制の改革
江戸時代初期、各藩の給与体制は、地方知行制が主流でした。これは、家臣に土地と付随する百姓(地方)を分け与え、その土地での経営と年貢の徴収(知行)を任せる、言わば旧来の封建的システムです。この体制では、組織体制のヒエラルキー化が進み、藩主が直接指示を出すことができる直属の家臣が少なくなります。
正之は、これにメスを入れ、蔵米渡し制に移行します。これは、藩が土地を一括で経営し、家臣の身分に合わせて、収入を配分するシステムです。これにより直轄地と直属の家臣を増やすことに成功し、中央集権化を達成しました。
②蒲生氏郷の商業政策の踏襲とアレンジ
正之は、蒲生氏郷時代から重きをなした商家、特に簗田家を中心とした検断を温存し、商業政策を踏襲します。これは、既に確立していた会津の商習慣を活用することで、物資の需給や価格などの統制を取りやすくする狙いがありました。
また、新たに追加された政策として留め物・津留があります。これは、藩の許可がないと、藩外に輸出できなかった制度で、対象は特産品や必需品でした。これも需給や価格の統制を取るために行われた施策です。
③常平倉・社倉
正之は、上記の留め物・津留にもあった通り、物資の需給・価格の安定化に心を砕きました。その中でも、米に対しては特に力を入れ、常平倉・社倉を導入しました。常平倉は公費・社倉は庶民のお金で運営される米蔵で、豊作の年は米を買い入れ備蓄し、不作の年は米蔵から流通させることで、米価の安定と飢饉対策を行いました。
のちに述べる、家訓十五条には社倉についてこの様に述べられています。
『一、社倉は民のためにこれを置き、永く利せんとするものなり。 歳餓うれば則ち発出してこれを済うべし。これを他用すべからず。』
④家訓十五条の制定
正之は、以降の藩主とその家臣達が守るべき掟として、家訓十五条を制定しました。天皇を敬い、幕府に忠節を誓うこと、上下身分をわきまえる事、公正な政治を行い法に従う事、秩序や組織を乱してはならないことなど、言わば会津藩の経営理念となる重要事項を十五箇条に渡って纏めています。
一、大君の儀、一心大切に忠勤を存すべく、列国の例を以て自ら処るべからず。若し二心を懐かば、則ち我が子孫に非ず、面々決して従うべからず。
一、武備は怠るべからず。士を選ぶを本とすべし。 上下の分、乱るべからず。
一、兄を敬い、弟を愛すべし。
一、婦人女子の言、一切聞くべからず。
一、主を重んじ、法を畏るべし。
一、家中は風義を励むべし。
一、賄を行い、媚を求むべからず。
一、面々、依怙贔屓すべからず。
一、士を選ぶに便辟便侫の者を取るべからず。
一、賞罰は家老の外、これに参加すべからず。若し出位の者あらば、これを厳格にすべし。
一、近侍の者をして、人の善悪を告げしむべからず。
一、政事は利害を以って道理を枉ぐべからず。僉議は私意を挟みて人言を拒むべらず。思う所を蔵せず、以てこれを争そうべし。甚だ相争うと雖も我意を介すべからず。
一、法を犯す者は宥すべからず。
一、社倉は民のためにこれを置き、永く利せんとするものなり。 歳餓うれば則ち発出してこれを済うべし。これを他用すべからず。
一、若し志を失い、遊楽を好み、馳奢を致し、土民をしてその所を失わしめば、則ち何の面目あって封印を戴き、土地を領せんや。必ず上表して蟄居すべし。
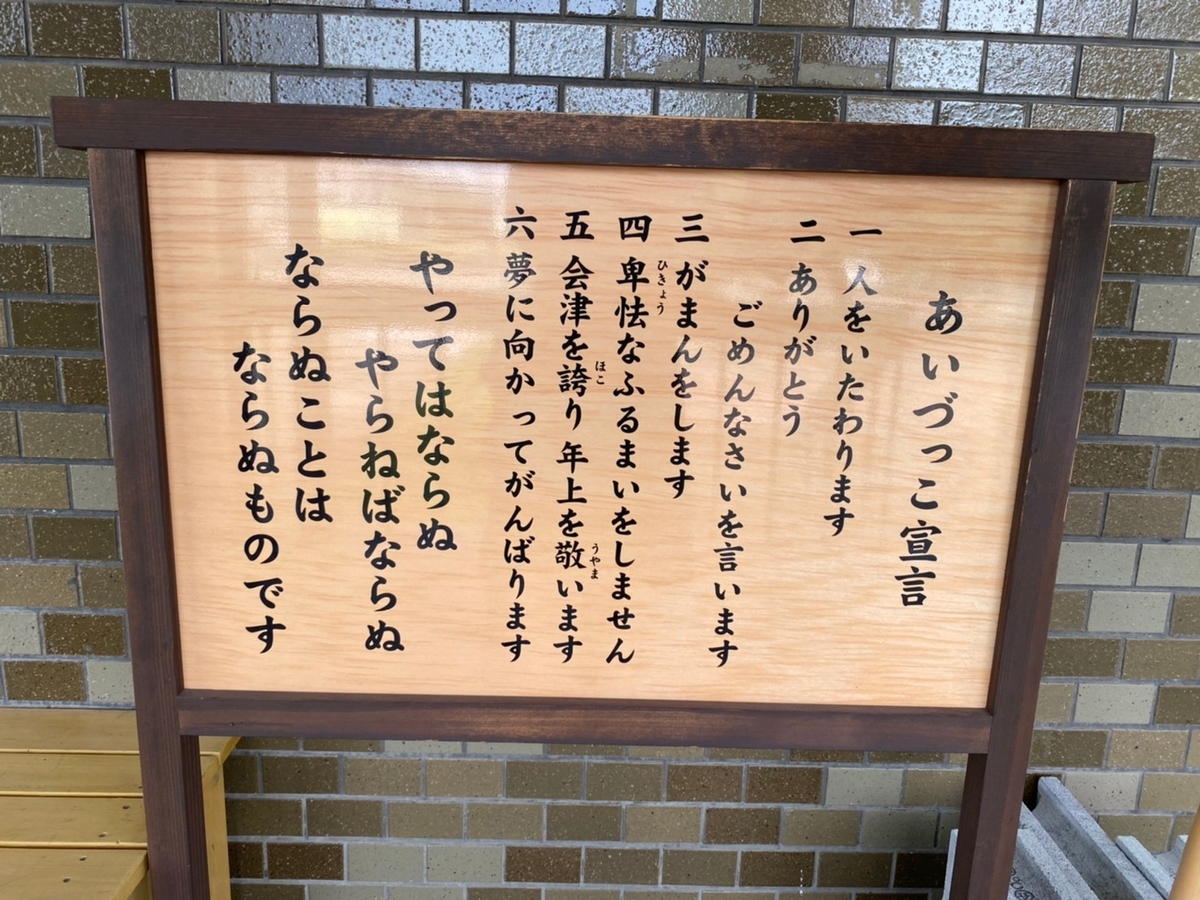
④学問の普及
正之は、藩学(藩が公認する学問・思想)を朱子学としました。朱子学は、儒学の一派ですが、上下身分や秩序を重んじる学問で、家訓十五条の精神もこの儒学の影響を色濃く反映しています。正之は、藩の教育水準を高めるべく、豪商倉田家出身で著名な儒学者である横田俊益(よこたとします)を起用します。横田俊益は稽古堂を設立し、そこでは儒教・詩文・国文・医学など幅広く講義が行われました。身分を問わず様々な人々が集まったので、一般庶民に向けた日本最古の私学校と言われています。
一方で、心学(庶民の間で流行った学問)は、近江聖人と呼ばれた中江藤樹を始祖とする藤樹学(陽明学)でした。江戸時代初期に、会津から若い優秀な町医師が京都に学問に行き、この藤樹学を学んで持ち帰ってきた事が始まりです。実は、この藤樹学は、朱子学を批判する形で生まれた学問であるため、一時は禁止されましたが、会津で行われた学問は、専ら庶民の道徳教育にのみ主眼が置かれている事が理解され、禁止が解かれる事となりました。
藤樹学の学者は、庶民からも尊敬の眼差しで見られ、藩の統治にも大きく貢献したために藩から表彰される人物もいたそうです。
このように、保科正之は、家臣への給与体系の整備・領民の食料などの生活安定・教育水準の確保・家訓による藩の理念の明確化など、人々の生活を安定させ、指針を定め導くシステムを構築する事に長けた指導者でした。このような仕組みが最も優れている点は、代が変わっても安定した統治・経営を継続する事ができるという点です。彼が構築した優れた藩の組織こそが、会津藩を以後220年以上に渡り力強く支える屋台骨となったと思います。
さて、本当は江戸時代後期の会津藩と会津商人についても語りたいのですが、今回の旅行時には知識がなかった事もあり、事前に取材コースに組み込むことが出来ませんでした。また、改めて会津を訪ねる際のお題として、ここでは項目と概要の紹介に留めておきたいと存じます。
・松平容頌と家老田中玄宰
5代目藩主松平容頌(まつだいらかたのぶ)と田中玄宰(たなかはるなか)は、天明の大飢饉や藩の赤字財政の苦境から、会津藩を立て直した中興の立役者です。蒲生氏郷・保科正之時代に生まれた特産品に更に改良を加え、更に養蚕や薬用人参といった新たな特産を育てたことで知られています。また、会津藩士のための学問所、日新館の建設とその過程で大活躍した会津商人の須田新九郎の物語など、興味深いエピソードがたくさんあります。
youtu.be日新館の上空からの撮影動画(引用:會津藩校日新館様HP)会津藩の藩士は10歳を迎えると、日新館で文武の修練を積んだ。武術や医学、天文学のみならず、水練用のプールまで完備されており、学生も1000人以上に及んだ。優秀な学生は江戸や他藩への留学も許されたとのこと。
・藤樹学
前述の通り、会津の心学の主流は藤樹学と言われています。藤樹学は、利己主義を捨て、利他の精神を持つことを中心とした教えです。喜多方から京に学びに行った町医者たちが持ち帰ったことをきっかけに、喜多方を中心に地元の農民・商人・男女を問わず、一般庶民の教養として広く広まりました。
実は、近江商人の三方よしに代表される精神も、この藤樹学にルーツがあるとされており、ここでも近江と会津の深い縁を感じずにはいられない発見で、非常にテンションが上がりました!!
この話をもっと深掘りしたかった!改めて会津に行く際は、喜多方にまで足を伸ばして藤樹学巡りをしたいです!

豊臣政権末期に、蒲生氏郷によって会津にやってきた近江商人の技術、そして江戸時代初期に会津に持ち込まれた藤樹学。近江発祥の文化や思想が、別々のルーツを辿って、会津の地で再び巡り会っていました。
このような、奇跡の巡り合わせに出会える事が、歴史を学ぶ上で最もスケールとロマンを感じる瞬間だと思います!!
幕末から明治にかけての会津では、会津藩が会津戦争に敗れたことで、鶴ケ城や御薬園、土津神社といった、今に遺る歴史遺産や土地が明治新政府軍に略奪・接収され、荒廃していました。これに対し、古くからの会津の豪商達が私財を投げ打って、明治新政府からの土地の買い戻しや復興に貢献しました。
また、江戸時代の商人によくあることですが、藩や幕府と深くつながることで地位を築き上げた商家は、時代の変化に際しては政策や政権の変化の影響を大きく受けてしまいます。藩や藩士へのお金の貸し倒れなども多かったことでしょう。会津戦争で会津藩が敗れたことは、大きな痛手となったようです。
これらの事が、結果的に会津の豪商達の経営悪化と没落の一因となり、会津商人の記録の多くが失われてしまいまったと言われています。しかし、会津商人達は、明治維新の激動の時代に、自らの身を捨ててでも、会津の誇りを守り後世に受け継いだ立役者と言えるでしょう!
しかし激動の時代を経てもなお、会津商人の足跡を今に伝えてくださる方々が多くおられます。この旅では、そんな会津商人スポットを主に巡ったので、次回記事にて、書く事ができればと思います。

以上のように、今回の記事では、会津商人について、日本屈指の名君と名高い、蒲生氏郷・保科正之の両君の統治との関わりを中心に述べました。
先ほども少しだけ述べました通り、次回の記事では、実際に訪れた会津の名所や食べ物を中心に、旅の記録をメインに纏めた記事にしたいと思います!
余談:その時世界では
蒲生氏郷や保科正之が会津を治めていた16世紀末〜17世紀後半
ヨーロッパでは、ドイツ発の宗教改革の波がフランスに到達しており、フランス王家が保護するカトリックと新興宗派のプロテスタントの戦争である、ユグノー戦争が終盤を迎えていました。それまでの様に、プロテスタントを弾圧することでは抑えきれなくなっていたフランス王家は、1598年にナントの勅令でプロテスタントを公認することで、ユグノー戦争の収束に向かいました。
各自の職業を神から与えられた天職とし、善行(商売)の積み重ねにより神から救済されると説いた、プロテスタントの思想は、金儲けは悪として忌み嫌っていたカトリック社会の教義を大きく覆すものでした。
この商業の宗教的正当化が、17世紀にルイ14世の重商主義政策によるフランス最盛期の現出、さらには18世紀の西欧資本主義の発達にまで行き着く大きな時代の胎動を生み出す契機となりました。
実は、この商業に対する宗教観の改革は、江戸時代の日本においても仏教や心学の中で起きており、江戸時代の商業の活性化に貢献していました。
さらに言うと、私は、明治維新後の日本の急速な近代化は、日本で起きたこの“宗教改革”がもたらした、西欧資本主義に対する親和性が、大きな役割を果たしていると考えていて、これについてもいつか語ってみたいと思います!


